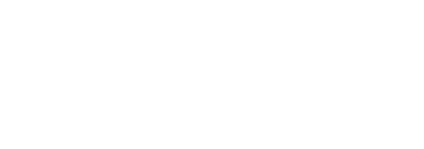COLUMN
[HRプロ連載記事]第11話:米倉誠一郎教授と日本のイノベーションを考える(後半)
8.連載記事
1998年に社会人デビューした私は、戦後の日本経済の大復興はもちろんのこと、バブルで好調期の日本経済を体験していない。トヨタ、ホンダ、ソニー、パナソニックなど世界に名だたるイノベーション企業が旗振り役となって、日本が世界を席巻していたのは学生時代のことだ。
その後、日本は2010年に名目GDP世界2位の座を中国に譲り渡し、今や3倍近くの差をつけられている。平成元年と平成30年の時価総額ランキングを比較した表がある。平成元年にはTOP30に21社日系企業がランキングしていたが、30年後にはなんとゼロになってしまった(トヨタが日本最高で35位)。そうした状況の中、この変化の激しい現代において、日本人が本来持っている力を発揮するにはどうすればよいのか。
そのヒントを得るべく、個人的にも長年お世話になっている、日本を代表する経済学者、米倉誠一郎先生を訪ね、共に議論させて頂いた。米倉先生は日本を代表するイノベーション研究の第一人者で、いまも日本中、世界中を精力的に飛び回り、組織に対するさまざまな生きた知見をお持ちの方である。なお、文字量の関係で2部構成とし、今回は、その第二部をお届けする。
INDEX
第二部:マネジメントの一番大事な仕事は、仕事に意味を付けるということ
日本は給料が安い
(稲垣)海外と比べて、日本は給与などの条件面はどうですか?
(米倉)低過ぎると思います。海外の友人からよく言われるのは、「日本人は資産形成ができていないから、リスクをとらない」ということ。20代からけっこういい給料もらっていると、30代の終わり頃にはある程度資産形成ができるのです。マンションも持ってるし、子供の教育費も目途が立っている。年間2,000万円くらいもらってたら、リスクをとって新しいことにチャレンジもできるんです。しかし、日本は年収が800万円くらいで、資産を持ってないから“社畜”になってしまい、会社から離れられない。リスクをとりたくてもとれないんです。日本の低賃金化が、ボディブローのように効いてきているように思います。
先日も、「日本をイノベーションのハブにしよう」という人たちの話を聞いたのですが、そうすると、「じゃあ、シンガポール大の卒業生とかインド工科大学の卒業生に3,000万円払えるの!?」という話になってくるのです。おそらく難しいでしょう。でもそれができなくては、イノベーションのハブにはなれない。日本は過去、安い給料でも十分強かったのですが、今はそれじゃ勝てないんです。
少し前に中国系のTech企業が日本に来て、初任給40万出すと言ったのが大きな話題となりましたが、でもあれは中国のIT企業では普通なんです。今の多くの大企業の新卒も、初任給は20万そこそこで、諸君の若い頃と同じなんです。初任給が20年間変わっていない。そんな国ないですよね。韓国だって20年前と比べて、GDPは3倍になっています。アメリカだって2.5倍、ドイツだって1.5倍、中国は20倍。それに伴い、当然給料も上がってます。日本は全く変わってないじゃないですか。この異常さにみんな気づいてないんです。こんなマインドセットじゃ戦えない。優秀な人材を取り込めるはずがないんです。
(稲垣)3年前、インドネシアのトップ大学の1つ、インドネシア大学で、キャリアビジョン研修を実施したんですが、受講生の覚悟を求めるために、一人当たり5万ルピア(日本円で約400円)ずつのお金をいただきました。インドネシアの学生からすると結構なお金です。それでも自己成長に意欲的な学生が多く集まり、定員の40人はすぐに埋まりました。案の定、皆とても優秀でした。しかし彼らは、日本企業に就職するという選択肢は全く持ち合わせていませんでした。自分で起業するか、官僚になるか、もしくは、政府系・財閥企業・アメリカのオイルメジャーなどの給料のいいところを狙っていました。ある受講生からは、はっきり言われました、「日本は選択肢にない」と。
(米倉)そうですよね。私だって絶対行きません。給料も安い上に、日本人しか偉くなれないなら、行く意味ないですからね。
君ならできる、必ずできる
(稲垣)とは言っても、日系企業も急に給料を上げられるわけでもないので、優秀な人材を採用するというのは、本当に難しい問題です。
(米倉)中小企業でも、海外に行った日系企業でも、世界の戦況から見るとどちらも遅れているんだから、優秀な人がこぞって来てくれるという状況ではないわけです。それならば、いまいる人材をうまく活用しなくちゃいけない。彼らの“いいところを見抜く”じゃなくて、“良くても悪くても強い人材にしなきゃいけない”んです。 松下電器だって設立当初のオンボロな企業にいい人材なんて集まるわけなかった。後に松下電器の副社長・技術最高顧問を務め、この会社の成長を支えた中尾哲二郎も、当時は、下請工場で働いていた“ただの人”だったんです。けれど松下幸之助が素晴らしかったのは、そんな彼を「きみならできる、必ずできる」と言って励まし、時には怒り、時には微笑みかけ、見事に“一流の人材”へと成長させていったんです。
そこを理解せず、「いい人がいない」といっているのは、マネジメントを放棄してることと同じです。良い条件を出せずエリートが来ないなら仕方がない。「じゃあどうすればいい?」と自分に問うてみたらいい。いい人材はただ待っていればくる来るものじゃない。いまいる人間をおだてて、すかして、木に登らせることこそが、マネジメントじゃないですか。来ないのなら、それをやるしかないんです。松下幸之助の話になるといつも、「それは松下さんがすごかったんだ」、「神様だから呼び寄せられたんだ」ってことになるけど、僕はそうじゃないと思う。松下幸之助のすごいところは、「できないやつを、みんなできるようにした」ということなんです。
仕事は意味付けだ

(稲垣)米倉先生の新著、「松下幸之助:きみならできる、必ずできる (ミネルヴァ日本評伝選)」を私も拝読し、「きみならできる、必ずできる」という名言を知りました。この言葉はすごいですね。
(米倉)「どんな仕事にも意味付けをする」というのが、マネジメントにおいて一番大事な仕事じゃないでしょうか。ですから、従業員に「いまあなたがしている仕事はこのような意味があるのですよ」と、その意味をきちんと伝えていなきゃいけないと思います。それを伝えれば、従業員はやる気が出るし、伝わらなければ、やる気は出ません。
よく言われるのは、二人の石工の話ですね。石を削っている人に「何をしているんだ?」と訊いたら、「このくそいまいましい石を削ってるんだ」と返ってきた。で、もう一人の人に何をしているのかと訊いたら、「いま、世界で一番美しい教会の基礎の部分を作っているんですよ」と返ってきた。二人の仕事は、はたから見たら、同じ仕事なんです。だけど、一人には「お前、ここ削っておけ」と、部分図しか見せておらず、もう一人には「この石を削ると教会のこの部分になるから」という風に、“仕事の意味”がきちんと与えられていたんです。だから、どんなボロ工場であっても、「俺たちはこういう風にやって世界をこういう風に変えて、だからお前の仕事はこういう意味があるんだ」という風に、ちゃんと仕事に意味付けをしてあげるようなマネジメントをやっていれば、従業員の仕事ぶりは、全然違ってくるんですよね。
つまり、今の日本のマネジメントは、そこを忘れているんです、 “心の琴線に触れるようなフレーズ”を従業員に伝えてあげることを。マネジメントって一番大事なのはそこじゃないでしょうか。松下幸之助で言うところの「きみならできる、必ずできる」です。このように声をかけてあげれば、従業員は必ず、「じゃあやってやろう!」となりますから。マネジメントのセンスは、従業員の心の琴線に触れられるセンスと言ってもいいでしょう。
世界に誇る日本のトータルクオリティコントロール
(稲垣)日本人の素晴らしいところはどこでしょうか。
(米倉)やはり、仕事のクオリティの高さというものがあると思います。これは急に生まれたものじゃなくて、さまざまな前提の大きな積み重ねから生まれてきたものを日本のマネジメントが追及してきたことなんじゃないかと思います。ただ単に「これをこうしなさい」、というマニュアルがあるのではなく、「その工程の前はどうなっているんだ、その前はどうだ」といって徹底的にクオリティにこだわった結果、日本特有の「トータルクオリティコントロール」という概念が生まれていったんじゃないでしょうか。
最初は単に、どうすればうまく作業できるかだけを追求していたけれど、それだけじゃやっぱり質は良くならなくて、価値観や理念をどういう風に共有しておかなければならないのかとか、インセンティブはどうするのかとか、事故が起こったときに、誰にラインを止める権利を与えるのかとか、また、自分が意思を持って判断したことをちゃんと評価しようとか。そういうことをじっくりじっくり積み重ねてきて、日本企業は強くなったんですよね。その途方もない積み重ねが厚い層となって、日本は他国が真似することのできない強さを作ってきたんだと思います。
日本人へのメッセージ
(稲垣)最後に、日本人に向けてメッセージをお願いします。
(米倉)まだまだ、世界の現場は改善すべきことがあるし、日本の過去の経験にもいいものがある。そして今や通用しないものもあります。短絡的に、昔はこうしていたという押し付けや、思考を停止したど根性主義はもう通用しません。長靴を履いて現場を回って、Socialize(社交的活動をする)して、Shared Value(価値観共有)を浸透して、一人ひとりの創意工夫を愛でて、基本的につまらないルーティンワークの中にどれくらい喜びを見いだすか。そういったことに今まで以上に力を注がなくてはなりません。
日本人は、かっこよく言えば、知のEnabler(自立を促す存在)なんだと思います。いろんなナレッジを持っている人たちの触媒になって、それらをもっと大きく開化させる、それが世界における日本人の役割です。欧米人だったら、食事を摂りながら仕事をするとか、所長が現場に出てくるなんてことはなかったけど、日本人はやりますね。それはカッコいいとかカッコ悪いじゃなくて、何のためにやってるかといったら、そうしたことで、仕事に意味付けをしてきたんです。そういうことに我々日本人は長けていたんです。過去形ですがね。何にしても、Socializeして現場をと近い距離感を作って、仕事に意味付けをしてあげる人間になるリーダーになる、というのが大事ですね。
このことに関連して、孟子がすごくいいことを言っています。「普通のリーダーはこれは俺がやったと言う。優れたリーダーは民衆がやったと言う。真に優れたリーダーは『これは私たちがやった』と民衆に言わせる」と。日本の真のリーダーはこうあるべきじゃないかと思うんですよね。従業員たちに、「これは私たちがやったんだよね」って言わせるんです。つまり、常に仕事に意味付けをしてあげる伝道師たれと。
いまは、かつて勝てたときの喜びを、みんな忘れちゃってるんです。仕事は勝ってなんぼなんですよ。それはインドネシア人に教えるところじゃなくて、本当は日本人に教えなきゃいけないんでしょうね。勝つっていう喜びを。
取材協力:米倉誠一郎(よねくら せいいちろう)さん
1981年一橋大学大学院社会学研究科修士課程修了。1990年、ハーバード大学にてPh.D.(歴史学)を取得し、1997年より一橋大学イノベーション研究センター教授。1999年~2001年および2008年~2012年3月まで、同センター長。2012年3月よりプレトリア大学ビジネススクール(GIBS) 日本研究センター所長を兼務。現在、法政大学、一橋大学の他に、Japan-Somaliland Open University 学長をも務める。企業経営の歴史的発展プロセス、とくにイノベーションを中心とした経営戦略と組織の史的研究を主たる研究領域としている。経営史を専門とする一方で、関心領域を広く保ち、学際的であることを旨としている。季刊誌『一橋ビジネスレビュー』編集委員長、及びアカデミーヒルズにおける日本元気塾塾長でもある。『経営革命の構造』(岩波新書)、『創発的破壊:未来をつくるイノベーション』(ミシマ社)『イノベーターたちの日本史:近代日本の創造的対応東洋経済新報社』(東洋経済新報社)、『イノベーターとしての人間・松下幸之助』(ミネルヴァ書房)など、著書多数。
本コラムは、HRプロで連載中の当社記事を引用しています。
https://www.hrpro.co.jp/series_detail.php?t_no=1668&page=1