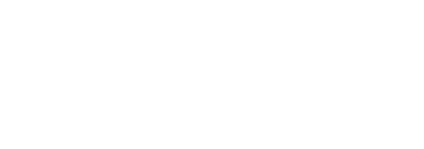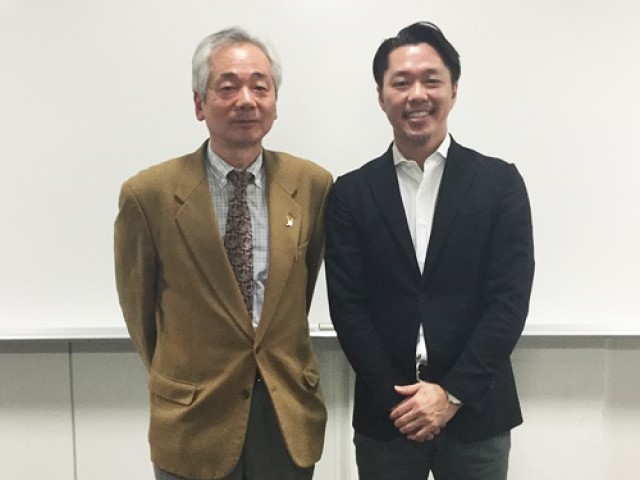COLUMN
[HRプロ連載記事]第34話:日本のグローバル化へのカギは「模倣からのオリジナリティ」
8.連載記事
今回の対談のお相手は、立命館大学経営学部の守屋教授だ。教授は、「学校」という枠組みを飛び出して、ベンチャーキャピタルからスタートアップなどさまざまな組織と交わり、実学として知見を貯められている。私も何度か対談をさせていただいたが、スタートアップの端くれとして、毎回背筋が伸びる思いである。いま、「日本はダメだ」、「日本は取り残されている」という暗い話を聞くことも多い。しかし、教授は「日本の未来は明るい」と話す。オプティミストな守屋教授の底抜けの明るさで、2022年を勢いよくスタートさせるべく、1月と2月の2話にわたって対談の模様をお送りしたい。
INDEX
日本は今後どのようにグローバル化していけばよいか
稲垣:本日はさまざまな角度からお話をうかがいたいと思います。このコラムのテーマが「日本のグローバル化への挑戦」ということで、いきなり本題ですが、日本は今後、どのようにグローバル化していけばよいのでしょうか。
守屋:ちょうど昨日、ベンチャーキャピタルのWiL社を、アジア太平洋研究所のオンラインセミナーにお迎えしてお話を聞いたところです。全体を通して大変興味深かったのですが、中でも日本の大きな課題だと思った点は、「日本のスタートアップへの投資」というところ。グロース企業投資がようやく日本で拡大してきているのですが、まだまだ成熟化しておらず、「上場すると、いきなり売上高を上げて営業利益・純利益の拡大」という、右肩上がりのシナリオが要求されるんです。しかし新興企業かつ成長型企業というのは、売上高は倍増していっても、研究開発投資や海外展開といったことを考えると利益が立たないんですよね。例えばシリコンバレーの企業。Amazonなんかが代表格ですが、もう何年、何十年と株価・売上高は高水準であるものの、「営業利益は上がらない」とか、「純利益なんか存在しない」、「配当なんかしない」などという会社も多く見受けられます。そのため、日本がグローバルで競争していくには、スタートアップからマザーズへと更に大きく成長していく段階における、「投資家群をどう育成するか」というのが課題ですね。
稲垣:2022年から東証が廃止されてグロース市場になりますが、グロース市場のひとつの新しい指標に「成長率」がありますよね。そこがひとつの明るい兆しだなという気はします。
守屋:そうですね。そういう意味では、メルカリやスマートニュースなど、アメリカでも事業展開をしているベンチャー企業、グロース企業のあり方が、今後の日本経済の起爆剤になってくると思います。どうしても、国内マーケットだけの閉じたかたちでベンチャーをやっていると、いずれ成長限界がやってくる。しかもそのグロース企業そのものが日本化し、「終身雇用」や「年功序列」、「長期雇用」といった話になると、成長性を失ってしまうんですよね。メルカリやM3のように、日本で展開しながら日本だけでなくグローバルで売上高を伸ばしているような、いわゆるボーングローバルが成長し、10年から20年で上位の顔ぶれが大きく変わってほしいと感じています。
稲垣:例えば私がいたインドネシアでいうと、いまやユニコーン企業(評価額が10億ドル超)はざらで、デカコーン企業(評価額が100億ドル超)が出てきているんですよね。Gojekというのは、いわゆるUberと同じようなビジネスモデルを展開している企業ですが、急成長しているインドネシアの内需だけでなく、アジアを視野に入れてモデルを作っています。Gojekはマレーシア発のGrabと競合しており、「東南アジアをどう取るか」という競争をしていますが、もうマーケットは自国で閉じていませんね。
守屋:そうですね。そのため今後の日本のベンチャー企業・グロース企業の大きな課題は、そのように「開かれたかたちで大きくやれるか」、「日本の大企業がグロース企業に対してどうインベストメントしていくか」ということです。日本の大企業は、山ほど内部留保を持っています。その内部留保をドカーンと吐き出して、新興企業に対して大胆に投資を行っていく。それによってスタートアップからマザーズに上場し、更にスタンダードを飛び越えてプレミアのようなかたちのマーケットになって、何兆円企業に成長してくる。大企業はそういった企業に投資する。実は日本の大企業の多くが、もう自社のビジネスだけでは儲からなくなってきているんですよね。不動産投資をやってみたり、場合によってはそういったスタートアップ投資を始めたりしています。かつて富士電機から富士通が生まれたり、豊田織機からトヨタが生まれたりしましたが、まさにそのようなプロセスだと思うんです。大企業の内部留保で、日本のグロース市場を育てるべきだと思いますね。

「GAFA」のような企業が日本で育たない理由
稲垣:先生は、「日本ではGAFAを育てなくてよい。もう少し小ぶりのメガベンチャーを育てるべきだ」とおっしゃっていますよね。その背景をお聞かせいただけますか?
守屋:まず理由の1つは、プラットフォームビジネスだということです。なぜ日本にGAFAのような企業が誕生しないかというと、日本の企業はもともと、アメリカほど多国籍化していないからです。ほとんどは「グローバルだ」と言いながらも、その範囲は東南アジアや中国、アメリカ、ヨーロッパくらいで、実際には総合商社などのレベルの企業でしか、本当の意味でのグローバル化をしていません。そういった諸状況の中では、GAFAのような企業は誕生しづらいということが言えます。
また、もう1つの要素というのは、日本の国家に軍事力や外交力といった、多国籍展開ができるような基礎能力がないことです。昨日(先述のWiL社との対談)でも少し話題になりまして、「日本でもGAFAが生まれる」というような話をしていましたが、そもそも国家が持ち得る条件が、アメリカとそれ以外の国では違うんですよね。唯一、可能性があったのが中国だったわけですが、中国はやはり、国家社会主義体制の中で政府を凌ぐような力を持つことや、政府を凌ぐようなかたちで情報を握ることに対しては、強い敵対感や統制感が強い。そのため、アリババやテンセントほどの大規模な企業が、国家によって抑えられたわけですよね。そうした事情から、アメリカのようにGAFAクラスの企業を持てる国であったはずの中国が持てなくなったため、今のところはGAFAの一人勝ちになっているんです。そこに関して、日本はそれほどの大きな国家としての外交力や経済力、軍事力を持ち合わせていないですし、そもそも今日の軍事力というものはデュアルユースなんですよね。軍と民間企業が融合し合ってハッキングをするとか、コントロールをするとか、宇宙空間においてサイバー防衛やサイバー攻撃をするような世界になってきています。そのため、そもそも日本が平和憲法のもとで、かつアメリカの安全保障の枠組みの中で存在している以上、そういった軍事力を持った他国の企業を超えるようなかたちで展開できるかというと、どうしても無理があるわけです。
稲垣:なるほど。やはり国家の覇権力というものが関係するんですね。
守屋:そうです。ベースに軍事力があって、外交政治力があって、経済力がある。また今日の軍事力というのは、軍と民間企業とがデュアルユースなかたちで結びつきあい、常にサイバー上において攻撃を加え合っているんですね。ですからそういった状況の中では、日本は局外者みたいなものなんです。

稲垣:外交力、軍事力、経済力を持っている国は、アメリカや中国以外にもありますか?
守屋:ないですね。ですから中国が賢かった点は、デュアルユースの枠組みの中でIT分野に関しては閉じたというところです。それによって、自国のGAFAを育てようとしたんです。
稲垣:内需にしたんですね。
守屋:日本がやろうとしても、マーケットが小さいためにできないんですよ。中国の場合は14億人ほどのマーケットがあるためそれが可能になり、さらに一帯一路の枠組みでかなり大きな経済版図を持ち得るので、そこを飲み込むかたちで軍事産業を融合させながら展開し、国家そのものがGAFAになろうとしているんだと思います。
稲垣:そのシェアの広げ方は内需だけではなく、一帯一路で近隣諸国に対してマーケットを広げていくことで、国家主導でGAFAのようなことをやっているということですかね。“中国GAFAの一事業部”がアリババだと。
守屋:一事業部ですね。ですからアリババでも、経営者のジャック・マー氏が追放されて中国の国有企業の幹部が内部に入り込み、アリババが持っている国民の個人情報を国家統制に使う。他にも、例えば自動車配車アプリで知られるDiDiも、情報の塊ですからね。「誰がどこに移動して、何をしているか」が全部ばれてしまう。国家統制機関に置いて、アメリカでの上場を廃止させ、「香港市場に上場しなさい」という指導を国家がしています。そのような背景から、国家そのものがGAFAそのものになり、国家統制を行って情報を統一化させ、シングルユースによってデータベースを構築しようとしているんだと思います。そのほうが、ある面では効率的なんですよね。
日本の強みは、「模倣からのオリジナリティ」
稲垣:いま日本は、GDPが世界3位ですが、もう時間の問題でどんどん下がっていく。このような中で我々がどのようにしてグローバルで勝ち残っていけるのか、お聞かせいただけますか?
守屋:私達はもう一度、日本の歴史認識に立ち戻るべきだと思います。古来から中国という巨大文化圏があって、韓国があって、そのもとで日本が存在する。その中にあっては、中国文化を模倣したり、場合によっては平安時代のように、それをベースにしながらも自国文化を発展させたり、もしくは江戸時代のように鎖国して、日本文化を醸成したり。つまり歴史を1000年から2000年辿ってみると、常に大陸からの文化や技術の輸入の時期と、その熟成の時期と、更にその導入の時期と熟成の時期というのを常に繰り返しているんですね。
今はそれが中国とアメリカです。だから今、スタートアップなんだというかたちで、技術や文化を輸入・導入していき、日本的に発酵させていきながら、メルカリやスマートニュース、M3のように、独特のかたちで日本のサービスユースに置き換えていく。日本発で、「こんなのちょっと見たことないよ」というようなビジネスをドンドコドンドコ作る。さらにそれが進んでいくと、おそらく成熟期を迎えると思うんです。
稲垣:なるほど。日本には「模倣からのオリジナリティ」という形が文化としてあるんですか。
守屋:ありますね。それは平安時代でもそうで、例えば中国の場合だと漢字です。そこからひらがな文化ができていき、大和言葉から『源氏物語』などが出て、世界的に研究される文学ができ上がってきたわけですよね。ですから日本って面白い国で、導入して自分のところで発酵させて、それで世界ナンバーワンになるんですよ。戦後に「ジャパン・アズ・ナンバーワン」になったのも、アメリカから生産流通のノウハウを導入して、そのシステムを日本的に発酵させていった。それが若干発酵しすぎて、ちょっと熟れてしまったのが今という感じですね。
稲垣:『シン・ニホン』の安宅さんの本も、同じような論調で書かれていますよね。日本は模倣からのオリジナリティを作るのが上手という。
守屋:そうですね。安宅さんの主張でもそうですが、そこで最も大事な事柄は、世の中を変えていったのは常に若い世代だということです。明治維新にしても、戦後の焼け野原から創業した人達にしても、みんな大体若いんですよね。だから今を、令和維新といったかたちで考えるならば、先ほども申し上げた通り、日本の大企業がどんどん日本のスタートアップへ投資をしていき、新興市場を育成して、そして世界に展開していくのを、総合商社のような大企業が応援することが大切です。すると、おそらく「若いスタートアップやベンチャーで活躍している皆さん」、「年配者が組織を引っ張っている大企業の皆さん」というところで、住み分けが効いてくると思います。
稲垣:なるほど。日本の若者が変えていくのですね。

守屋:日本人は非常に手先が器用です。手先というのは脳に直結していて、それゆえに職人芸や職人技ができるのですが、アメリカ的、中国的な大雑把なものを導入し、細かく微細なかたちにするという部分では、イタリアによく似ているんですよね。ドイツ人も哲学やベンツなど、さまざまなものを生み出しますが、それをヴィトンやグッチ、フェラガモ、フェラーリといった高級製品に置き換えていくのが、イタリアなんです。
稲垣:なるほど。イタリア人と日本人は似ていますか。
守屋:似ています。ただ、イタリア人は1万円のものでも100万円で売るんです。対して日本人は、1万円のものは1万500円ほどで売るんですよね。ですから、全然儲からないという。
稲垣:フェラガモやグッチも、ブランド価値をつけて、ただの革製品を原価の何十倍の価格にしているわけですよね。そこは「日本の真面目さ」という1つのビハインドにもなってくる部分だということですね。
守屋:そうです。そういった部分はイタリアに学んで、「1万円のものをブランディングして100万円で売る力」というのを、これから身につけていった方がよいと思います。
※次月に続く
取材協力:守屋貴司(もりやたかし)氏
1962年生まれ。関西学院大学大学院商学研究科博士課程後期課程単位取得中途退学、立命館大学大学院社会学研究科博士課程後期課程修了。博士(社会学)。現在、立命館大学経営学部教授、立命館大学OIC総合研究機構・立命館大学経営学部事業継承塾副塾長所属。著書に『人材危機時代の日本の「グローバル人材」の育成とタレントマネジメント 「見捨てられる日本・日本企業」からの脱却の処方箋』などがある。
本コラムは、HRプロで連載中の当社記事を引用しています。
https://www.hrpro.co.jp/series_detail.php?t_no=2685